ドニ・ディドロ はフランスの哲学者で文人(1713 ー1784)。 哲学の面では、啓蒙の時代の一大プロジェクトだった『百科全書』を完成させた。文人としては、代表作に『ラモーの甥』や『ダランベールの夢』などがある。哲学と文学を結びつける役割を果たした。多くのブルジョワ劇を制作し、演劇の歴史に名を刻んだ。以下では、ディドロとエカチェリーナ2世の関係についても詳しく見ていく。
ディドロ(Denis Diderot)の生涯
ドニ・ディドロはフランスのシャンパーニュ地方のラングルで職人の家庭に生まれた。イエズス会の学校で学んだ。1729年、パリに移って、パリ大学で学んだ。
その後、ディドロは職を転々とした。演劇の世界に憧れたり、法律を学んだり、教会での説教者のために執筆を行ったりした。同時に、数学や哲学、英語などの勉学も行った。
その頃、ディドロはコーヒーハウスによく通った。ルソーやダランベール、コンディヤック、ラ・メトリらと交流を持つようになった。また、アンヌと知り合うようになり、1743年には父の反対にもかかわらず秘密裏に結婚した。
哲学者としての活躍:ダランベールとの『百科全書』事業
1745年には、英語の勉強が実り、ディドロは翻訳活動を開始した。イギリスのシャフツベリ伯の『人間の真価と徳に関する試論』を仏訳し、シャフツベリの思想をフランスに広めた。
1746年、ディドロはダランベールとともに『百科全書』の編纂を開始した。当初の計画は、1728年のチェンバースによる英語の百科事典『サイクロペディア』をフランス語に翻訳する予定だった。だが、この計画は途中で変わっていき、ディドロとダランベールのオリジナルの『百科全書』を編纂することになった。
文学と哲学の架橋
ディドロは『百科全書』の事業と同時に、他の著述活動にも打ち込んだ。様々なブルジョワ劇を制作し、演劇史に重要な貢献をした。
だが、『盲人書簡』を公刊した際には、無神論的な危険性を見出され、ディドロは投獄された。ディドロは理神論から無神論、唯物論へ移っていたと評される。
その後も、ディドロは著述を続けた。哲学と文学を架橋するような小説や演劇を制作した。小説では、『ラモーの甥』、演劇では『私生児』などを世に送り出した。美術や音楽など、文芸の評論も行った。
百科全書の完成に向けて
同時に、ディドロはダランベールとともに『百科全書』の制作を続けた。だが、『百科全書』は次第に批判を強く受けるようになり、弾圧や検閲の対象になっていく。
ただし、この対立構図については注意が必要である。伝統的には、これは『百科全書』という啓蒙の新しい知的プロジェクトと旧来のカトリック教会およびフランス王権と社会(アンシャン・レジーム)の対立とみなされてきた。だが、実際にはこれほど単純ではなかった。
注意すべきは、ニュートンやロックなどの近代的なイギリス哲学が当時のフランスでは広く認められていた点である。このイギリス哲学はフランスの啓蒙主義の代表者ヴォルテールがそれまでフランスで普及させてきたものである。
これを穏健的な啓蒙主義思想と呼ぶならば、たとえばフランスのイエズス会やパリ大学は穏健な啓蒙主義を受け入れていた。ローマ教皇ベネディクト14世もそうである。ただし、この新しい哲学への反対者は教会に存在した。とはいえ、『百科全書』への全ての反対者がイギリス哲学に反対だったわけではなかった。
複雑な対立構図
誰が『百科全書』の知的プロジェクトに反対したのか。啓蒙主義への反対者は『百科全書』に反対した。さらに、穏健な啓蒙主義者もまた反対に加わった。当初はそうではなかった場合もある。だが、ヴォルテールのように、途中から『百科全書』への反対に回ったケースもある。
なぜ穏健な啓蒙主義者もまた反対に加わったのか。主な理由は、『百科全書』に無神論や唯物論の要素が巧妙に埋め込まれていたためだった。当時のフランスでは16世紀と比べれば、宗教的寛容がより広く受容されていた。
それでも、無神論はなかなか受け入れられなかったのである。他方で、ロックやニュートンのイギリス哲学はキリスト教的な唯一神と対立して無神論に至ると考えられていなかった。
それでも、『百科全書』が本格的に弾圧の対象になるには時間がかかった。その理由として、『百科全書』が非常に浩瀚だったためである。その膨大で多様な内容を精査するにはかなりの時間がかかった。
他の理由として、ディドロやダランベールが編集や出版の際に危険な要素を露見しにくいよう巧妙にカモフラージュしたためである。
たとえば、ダランベールは『百科全書』のプロジェクトがロックなどのイギリス的な方針をとっていると明言している。
たしかに、『百科全書』はロックの項目を作るなどして、イギリス哲学の要素を含んでいた。また、 宗教的な項目については、伝統的立場の神学者に寄稿を依頼することもあった。
そのうえで、ディドロらは無神論的な要素を忍ばせた項目も作成した。このように『百科全書』は多様で膨大な項目を含んだので、その性格を十把一絡げにして理解するのは難しかった。このような仕方でディドロたちは巧妙にカモフラージュしたのである。
とはいえ、次第に、『百科全書』は無神論などの点で危険視され、反対者が増えていった。イエズス会やパリ大司教、ヤンセン主義者などがその危険性を宣伝した。
だが注意すべきは、この場合に、ロックやニュートンらのイギリス哲学は主な標的とならなかった点である。代わりに、『百科全書』は唯物論かつ無神論であり、宗教の敵だと断じられた。
ヴォルテールの離反
穏健な啓蒙主義の支持者もまた同様に『百科全書』の批判を行うようになった。当初、『百科全書』への反対や批判の声が高まっていく中で、ヴォルテールはディドロらに味方したその重要な執筆者の一人でもあった。
だが、『百科全書』の第七巻が公刊された頃には、ヴォルテールはこのプロジェクトから撤退することを決めた。『百科全書』に寄稿したそれまでの草稿や未発表の作品を返却するようディドロに強く求めた。
ヴォルテールが反対に回った一因は、『百科全書』でのイギリス哲学の扱われ方だった。ヴォルテールにはその扱われ方が過小であるように思われた。たとえば、スピノザの項目が22段にわたったのにたいし、ロックは4段だけだった。これは著名な哲学者の中でも特に短かった。
また、ヴォルテールはフランス宮廷でも『百科全書』への反対派が増大していることに気付いた。そのため、自らこのプロジェクトから身を引くだけでなく、ディドロとダランベールにもこれを終わらせるよう説得した。
パリ高等法院が本書への弾圧を開始した。1758年、ダランベールは『百科全書』の編集者の職を辞した。
ディドロにとっては苦しい状況が続いた。それでも、このプロジェクトを継続し、1772年、ついに合計28巻で完成させた。ルソーやモンテスキューなど、150人ほどの学者によって制作された大作である。これはフランス啓蒙の代表的な作品となる。
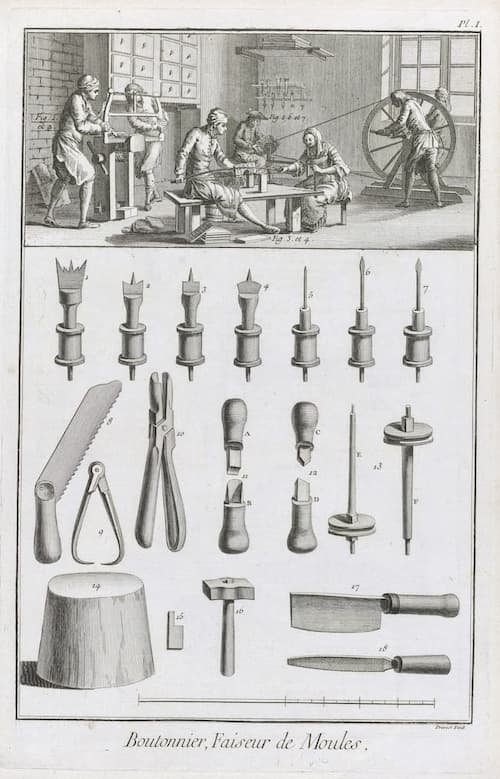
エカチェリーナ2世との関係
だが、この事業の完了により、ディドロは経済的に不安定になった。そこで、ロシアの女帝エカチェリーナ2世が彼を経済的に支えた。
エカチェリーナは啓蒙専制君主を自認していた。パリに図書館を設け、その司書にディドロを任命した。そのうえで、エカチェリーナはディドロにロシアへ来るよう何度も招待した。
ロシア訪問
1773年、ディドロはすでに高齢であり、病を患っていた。だが、この処遇への感謝を示すべく、サンクトペテルブルクを訪れた。4ヶ月間滞在して、40回ほどエカチェリーナと会談を重ねた。
ディドロはエカチェリーナを通してロシアの啓蒙主義的な社会改革に貢献しようとつとめた。ヴォルテールらもその成功を期待した。
ディドロとエカチェリーナのやり取りをより詳しく見てみよう。エカチェリーナはフランス語も流暢であり、ディドロとフランス語でやり取りした。サンクトペテルブルクに到着した当初は、ほぼ毎日、数時間にわたって両者は会談した。
ディドロは礼儀をわきまえず、エカチェリーナの太ももを何度もつねりながら、お世辞と批判を彼女に浴びせた。社会改革としては、法の支配の導入や、エカチェリーナも当初望んでいた農奴解放などを推進した。
ディドロは次第にロシアの気候に合わずに体調を崩すようになった。そのため会談の頻度が減っていった。ついには身体が自由に動かなくなってきた。社会改革の望みも明るくはなかった。そこで、ディドロは帰国の途についた。
帰国後の関係
ディドロはフランスに戻ってからも、エカチェリーナと書簡で交流を続けた。エカチェリーナは聡明な女性であり、読書などを通してディドロらの理論を理解した。だが、ディドロらへの明確な侮蔑をしばしば示した。
エカチェリーナは啓蒙主義の社会改革から次第に離れていった。たとえば、1773−75年のプガチョフの反乱により、農民には憐れみよりも敵意を向けるようになった。そのための農奴解放の計画は消えた。さらに、ポーランドを分割し、オスマン帝国と戦争を繰り広げ、クリミア半島を併合した。
ディドロはこれらへの厳しい批判を行わなかった。オスマン帝国との戦争を推進していたのも一因である。エカチェリーナがロシアで拷問を廃止したことを称賛した。だが、そのほかの残酷な処罰や仕業には沈黙した。
他方で、エカチェリーナは宮廷の私設ギャラリーのために美術品を買い入れるようディドロに依頼していた。このギャラリーはのちにエルミタージュ美術館となる。
ディドロは同時に著述活動を続けたが、1784年に病没した。
ディドロの主な著作・作品
『哲学断想』 (1746)
『盲人書簡』 (1749)
『百科全書』 (1751-72)
『自然の解釈に関する考察』 (1754)
『私生児』(1757)
『絵画論』(1765)
『ダランベールの夢』 (1769筆,1830刊)
『ラモーの甥』 (1761-74筆,1891刊)
おすすめ関連記事
おすすめ参考文献
鷲見洋一『編集者ディドロ : 仲間と歩く『百科全書』の森 』平凡社, 2022
冨田和男『ディドロ自然と藝術』鳥影社, 2016
Konstanze Baron(ed.), Diderot, le génie des Lumières : nature, normes, transgressions, Classiques Garnier, 2019
Robert Zaretsky, Catherine & Diderot : the empress, the philosopher, and the fate of the Enlightenment, Harvard University Press, 2019
Mogens Lærke(ed.), The use of censorship in the Enlightenment, Brill, 2009
