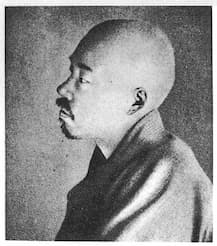正岡子規は明治時代の俳人で歌人(1867―1902)。日清戦争に記者として従軍してのちに病気を悪化させた。だが、残りの15年間ほどの期間で、俳句や短歌の世界に大きな革新をもたらした。夏目漱石と友人で、高浜虚子や伊藤左千夫らを育てた。以下では、海外での子規の評価も紹介する。
正岡子規(まさおかしき)の生涯:漱石との出会い
正岡子規は現在の愛媛県松山市で下級藩士の家庭に生まれた。本名は常規(つねのり)である。父を早くに亡くした。私塾で漢学を学び、松山中学校に入った。だが、1883年、政治家の道を志し、同中学校を中退し、叔父を頼って上京した。明治は立身出世主義の世の中である。子規もまた立身出世を望んだのだった。
1884年には、松山藩の常盤会給費生に選ばれ、第一高等学校に入った。そこで夏目漱石と交流をもった。また、この時期には短歌や俳句の制作を始めた。同時に、西洋から入ってきたベースボールに熱中し、これに「野球」の訳語を与えることになる。
1889年、子規は本郷の常盤会寄宿舎に入った。同年、初めて喀血した。1890年、1週間ほど喀血した。当時、ホトトギスは吐血するまで鳴き続けると信じられた。彼はこれにちなんで、「子規」と名乗るようになった。
文学の道へ
子規は帝国大学の哲学科に入り、国文科に移った。1892年には、新聞『日本』に『獺祭書屋俳話』を連載した。かくして、俳句の革新運動を開始した(この連載は1895年に『増補再版獺祭書屋俳話』として公刊される)。また、同郷で後輩の高浜虚子らへの指導を始めた。
写実主義へ
この頃、子規は大学の試験に落第した。1893年には大学を中退し、陸羯南(くがかつなん)が経営していた日本新聞社に入った。母と妹を東京に呼び寄せ、新たな生活を始めた。洋画家の浅井忠らと知り合い、彼らの写実主義に影響を受け、これを俳句に活かそうと決めた。
中国への取材旅行
1894年、日本は朝鮮や中国での権益拡大を図って中国と戦争した。1895年、子規はこの日清戦争に記者として従軍した。だが、病状がすこぶる悪化し、脊椎カリエスを患った。そのため、帰国後はほぼ病床で過ごすことになった。なお、帰京前に松山に寄り、当時松山中学校で教えていた夏目漱石のもとに短期間だが下宿した。
俳句と短歌の革新運動
子規は病身にもかかわらず、俳句と短歌の革新運動を本格的に開始した。1890年代の後半には、俳句革新のために、『俳諧大要』などの俳論を公にした。さらに、御歌所派を論敵として想定しながら、短歌の革新のために『歌よみに与ふる書』を公刊した。
子規は俳句にかんして、松尾芭蕉を高く評価していたものの、世間から過度に高い評価を受けていると論じた。同時に、与謝野蕪村の俳句への評価が低すぎると論じ、蕪村を高く評価した。そのようにして、俳句への評価基準にも変更を加えようとした。
『歌よみに与ふる書』
本書の冒頭部分が有名であるため、以下引用する。「仰おおせの如ごとく近来和歌は一向に振ひ不申もうさず候。正直に申し候へば万葉以来実朝以来一向に振ひ不申候」。すなわち、和歌は万葉集から源実朝までは大いに発展していただ、その後はそうではない、と。
実朝の評価
本書において、子規は次のように実朝の才能を高く評価している。実朝は政治の世界でも一流の人物となった。さらに、和歌の世界でもそうなった。この点で、実朝は例外的な人物である。
その歌についていえば、実朝の歌はただ器用というのではなく、力量や見識そして威勢がある。時流に染まらず世間に媚びない点で、当時の死んだような公家たちとは一線を画す。実朝は人間として立派な見識のあったからこそ、あのような力ある歌を詠むことができたのだろう、と。
実朝の後、子規からすれば、和歌は衰退してきた。しかも、今の歌よみの歌は昔の歌よみの歌よりも更に劣る、と。
紀貫之への酷評
さらに有名なのは『再び歌よみに与ふる書』の冒頭である。「貫之は下手な歌よみにて『古今集』はくだらぬ集に有之候」。紀貫之は伝統的に歌の名手とみなされてきた。子規がその貫之を下手な歌詠みと痛烈に批判したのである。
ただし、子規は貫之が彼自身の時代において下手な歌詠みだったというのではない(『 六たび歌よみに与ふる書』)。あくまで、子規自身の抱く文学的な基準からみれば、下手である、と。この文学的基準は古今東西の文学をみるなかで構築されたものとされる。
だが、子規はいまや『古今集』をバカバカしいものとみている。駄洒落か理窟っぽい歌しか見いだせない。貫之については、歌らしい歌はほとんど一つもない、と。
『古今集』について
『古今集』にかんしては、たとえば、子規は「月見れば千々に物こそ悲しけれ我身一つの秋にはあらねど」という歌について、こう批評している。これは『古今集』の中でも評判の高い歌である。子規からすれば、上の三句はすらりとして難がない。だが、下の二句は理窟っぽく蛇足である。
歌は感情を述べるものであって、理屈をのべるものではない。下の二句が「わが身一つの秋と思ふ」と詠よむならば感情的だ。だが、秋ではないがと当り前の事をいうので、理屈に陥っている。子規は理屈ではなく感情を元にするのが歌や文学だと考えている。
『新古今集』について
『新古今集』については、子規は『古今和歌集』よりは多少よいと言う。だが、優れた歌は指で数えられるくらいでもある。
『新古今集』の中では、子規は藤原定家に言及する。子規からすれば、定家には傑作がない。だが、相当に練磨の力はある。それ相応の名誉をえて、歌の門閥をうみだした。だが、この門閥が生じたる後は和歌は腐敗してしまった。その門閥の中で、歌の格や評価基準がかたまってしまったためである。
和歌刷新の意気込み
『六たび歌よみに与ふる書』では、子規は従来の和歌の刷新を目指していると宣言する。当時の日本では、従来の和歌を日本の文学の基礎として、その城壁とすべしと論じる者がいた。これにたいし、子規は従来の和歌をそのまま城壁にしようとするのは時代遅れだという。
明治の時代、軍備としては外国から大砲や軍艦を買う。そうして日本の防備をかためる。従来の日本の弓矢や刀は時代遅れである。同様に、文学でも
外国の文学思想などを輸入して、日本文学の城壁を固めるべきである。そのために、和歌についても旧思想を破壊して、新思想を導入するつもりだ、と。
その後、子規は伊藤左千夫さとともに、『日本』紙上で短歌に関する論考や作品を投稿していった。かくして、短歌をめぐる論争がそこで巻き起こることになる。
俳句と短歌の制作
正岡子規は自身の俳句や短歌を、高浜虚子が運営していた雑誌『ホトトギス』で公にした。新体詩なども制作した。
このように病身にもかかわらず、子規の活動は活発だった。しかし、子規自身は病気によってかつての立身出世の夢が潰えてしまったことを悲しく思ってもいた。悲運によって無名のまま没した父を自分に重ね合わせもした。
1900年代初頭、子規は『墨汁一滴』などの随筆も制作した。1902年に没っするまで、短歌や俳句の制作も続けた。それらは『寒山落木』や『俳句稿』、『竹乃里歌』に所収されている。
ちなみに、俳句といっても、子規は「発句は文学なり、連俳は文学に非ず」と述べている。すなわち俳句は文学だが、俳句を連ねたものは文学ではない、と。俳句という最小の定型詩をなぜここまで特別視したのか。
その答えとしては、子規が「せんつば」という一種の箱庭作りをこよなく愛したことにあると指摘されている。子規は小さい頃から没するまでこれを趣味としていた。この箱庭という小宇宙を作ることで美的感覚が養われたようだ。
この最小の定型的な小宇宙をつくることが愉しみと癒やしを与えてくれるごとく、俳句もまた愉しみと癒やしを与えてくれるものだった。
子規の俳句は高浜虚子らのホトトギス派に、短歌は伊藤左千夫(さちお)のアララギ派に大きな影響を与えた。
正岡子規の評価
子規の評価は様々ある。たとえば、近代の俳句や短歌の代表者の一人というのが最もポピュラーだろう。ほかに、明治という西洋文明の外的影響を否応なく強く受けた時代において、近代という新しい時代において、古来から存在してきた俳句や短歌のあるべき姿を問う挑戦者と評されている。
あるいは、様々な日本の伝統が動揺して様々な知的葛藤が生じた明治の時代において、子規はこの新たな大波の中で格闘し、その結果、近代的な強い個人へと発展した人物と評されている。
海外での評価
正岡子規はいまや海外でも知られており、近代日本の俳句や短歌の代表的人物として認知されている。たとえば、俳句では、子規は芭蕉や蕪村、小林一茶とともに日本の代表的な俳人と考えられている。
たとえば、次のような評価がある。子規は俳句において、親しみやすさと写実的な客観性、飾らなさと強さを組み合わせることで、従来の俳句に新たな内面的複雑さを吹き込み、近代俳句として成立させたとも評されている。
子規の海外での評価にかんして影響力を持つのは、やはり著名なドナルド・キーンの研究である。キーンは子規を公表している。そもそも、子規が俳句や短歌を制作し、その評論を行い始めた時期、俳句や短歌はほとんど時代遅れの産物とみなされかけていた。
子規とその弟子たちはこれらの伝統的な形式の中に新たな表現の可能性を見出し、活用した。特に、子規は写生という写実主義を採用したことで、日本の伝統的な詩歌に新たな風を吹き込み、このような画期的な役割を担った。今日の俳句や短歌への子規とその弟子の貢献や影響力は実に甚大である。そのため、子規は真に近代日本の詩の創始者である、と。
このような画期的人物という評価は近年も引き継がれえいる。たとえば、こう評されている。明治以降、日本は近代化の中で時代状況が激しく変化した。そのような状況で、外的な圧力に照らし合わせながら自分の感情を吟味し、内向きになり、行動に移るよりも沈思黙考するような小説が現れた。たとえば、二葉亭四迷や田山花袋らが挙げられる。この変化を俳句や短歌にもたらしたのが子規である、と。
正岡子規と野球
正岡と野球については、のちに斎藤茂吉が「子規と野球」で次のように述べている。「私は七つのとき村の小学校に入つたが、それは明治廿一年であつた。丁度そのころ、私の兄が町の小学校からベースボールといふものを農村に伝へ、童幼の仲間に一時小流行をしたことがあつた。東北地方の村の百姓は、さういふ閑をも作らず、従つて百姓間にはベースボールは流行せずにしまつた。
正岡子規が第一高等中学にゐてベースボールをやつたのは、やはり明治廿二年頃で、松羅玉液といふ随筆の中でベースボールを論じたのは明治廿九年であつた。松羅玉液の文章は驚くべきほど明快でてきぱきしてゐる。
本基(ホームベース)廻了(ホームイン)討死、除外(アウト)立尽、立往生(スタンデング)などの中、只今でもその名残をとどめてゐるものもあるだらう。
『球戯を観る者は球を観るべし』といふ名文句は、子規の創めた文句であつた。『ベースボールには只一個の球ボールあるのみ。而して球は常に防者の手にあり。此球こそ此遊戯の中心となる者にして球の行く処、即ち遊戯の中心なり。球は常に動く故に遊戯の中心も常に動く』云々に本づくのであつた。
明治卅一年、子規はベースボールの歌九首を作つた。明治卅一年といへば、子規の歌としては最も初期のもので、かの百中十首の時期に属する。
『久方のアメリカ人のはじめにしベースボールは見れど飽かぬかも』。子規も明治新派和歌歌人の尖端を行つた人であるが、『久方の』といふ枕言葉は天あめにかかるものだから同音のアメリカのアメにかけた。かういふ自在の技法をも子規は棄てなかつた。
また一首の中に、洋語系統のアメリカビト、ベースボールといふ二つの言葉を入れ、そのため、結句には、『見れど飽かぬかも』といふやうな、全くの万葉言葉を使つて調子を取らうとしたものである。
つまり子規のその時分の考へは、言葉といふものは、東西古今に通じて、自由自在を目ざしたものであり、その資材も何でもかでもこだはることなく、使ひこなすといふことであつた。
ベースボールの歌を作つたのなどもやはりさういふ考へに本づいたものであつた。それ以前にも『開化新題』の和歌といふものがあつたけれども、それと子規の新派和歌とは違ふのである。
『若人わかひとのすなる遊びはさはにあれどベースボールに如くものもあらじ』。これはベースボールといふ遊戯全体を讚美したものである。
『国人ととつ国人と打ちきそふベースボールを見ればゆゆしも』。競技が国内ばかりでなく、外国人相手をもするやうになつたことを歌つたもので、随筆に、『近時第一高等学校と在横浜米人との間に仕合マツチありしより以来ベースボールといふ語は端なく世人の耳に入りたり』云々ともある。
『打ち揚ぐるボールは高く雲に入りて又落ち来る人の手の中に』の結句『人の手の中に』はベースボール技術を写生したのであつた。『今やかの三つのベースに人満ちてそぞろに胸の打ち騒ぐかな』は、ベースといふ字をそのまま使つてをり、満基(フルベース)の状態を歌つたもので、人をはらはらさせる状態を歌つてゐる。一小和歌といへども、ベースボールの歴史を顧れば感慨無量のものとなる」。
正岡子規と縁のある人物
・ ・
正岡子規の『恋』の朗読の動画(画像をクリックすると始まります)
正岡子規の肖像写真
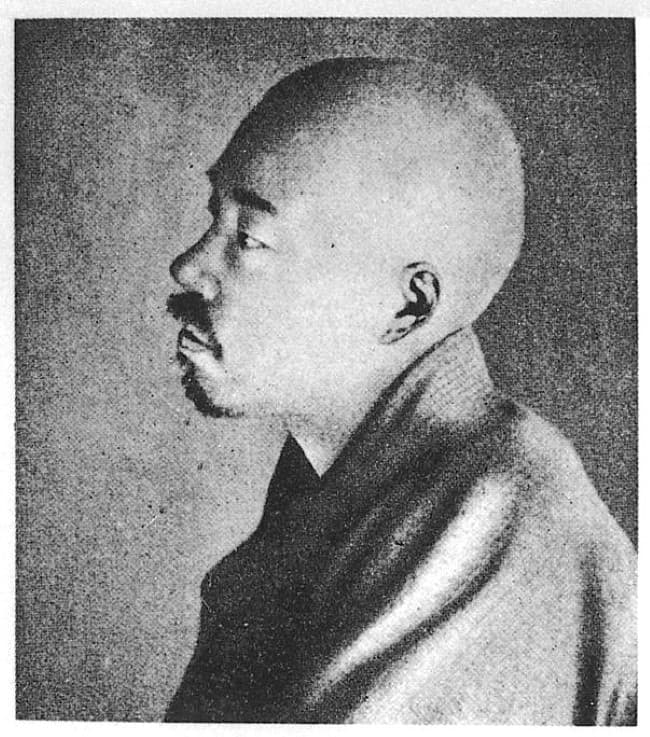
出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)
『くだもの』の朗読の動画
果物が大好きだった正岡子規
正岡子規の代表的な作品
『増補再版獺祭書屋俳話』(1895)
『俳諧大要』(1895)
『俳人蕪村』(1897)
『歌よみに与ふる書』(1898)
『百中十首』(1898)
『墨汁一滴』(1901)
『病牀六尺(びょうしょうろくしゃく)』(1902)
『仰臥漫録(ぎょうがまんろく)』(1901~1902)
『寒山落木』(1824−26)
おすすめ参考文献と青空文庫
復本一郎『正岡子規伝 : わが心世にしのこらば』岩波書店, 2021
坪内稔典『正岡子規 : 創造の共同性 』リブロポート, 1991
Janine Beichman, Masaoka Shiki : his life and works, Columbia University, 1974
Donald Keene, The winter sun shines in : a life of Masaoka Shiki, Columbia University Press, 2013
Rachael Hutchinson, Routledge handbook of modern Japanese literature, Routledge, 2019
※正岡子規の多くの作品は、青空文庫にて無料で読めます(https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person305.html)。