ナポレオン・ボナパルト1世はフランスの軍人で皇帝(1769−1821)。フランス革命で頭角を現し、クーデターで軍事政権を樹立した。ナポレオン法典の編纂などにより、フランスの近代化に貢献した。1804年にフランス第一帝政を設立し、皇帝となる。ワーテルローの戦いに敗北し、セント・ヘレナ島で没した。以下では、ナポレオンにかんする評価や、ナポレオンと日本の関係についてもみていく。
ナポレオン1世(Napoleon I)の生涯
ナポレオンはフランスのコルシカ島で弁護士の家庭に生まれた。フランス本土で教育を受けた。軍人の道を志し、陸軍士官学校で 学んだ。卒業後、砲兵少尉に任命された。
軍人としての成功:トゥーロン攻略
1789年、フランス革命が始まった。当初、ナポレオンはジャコバン派に属した。この時期はフランスとコルシカ島を行き来しながら、軍人として昇進していった。1793年、ナポレオンの一家はフランス本土に移った。
この頃には、フランスの王党派軍と、革命派の国民公会軍が戦いを始めた。国民公会軍はマルセイユを占領した。トゥーロンで、王党派と同盟したイギリス軍と戦った。
その際に、ナポレオンは国民公会軍の砲兵隊指揮官に任命された。トゥーロン攻略で頭角を現し、准将に昇進した。
1795年、パリでは、王党派が反革命のための反乱を起こした。ナポレオンはパリに戻っており、この反乱の鎮圧で活躍した。革命政府の信頼を得た。
イタリア遠征:カンポフォルミオ条約
ナポレオンはイタリア駐屯軍の最高司令官に任命された。イタリアで快進撃を続けた。ニースやサヴォワをフランスに併合した。イタリアでは共和主義者の活動を後押しした。
ミラノを支配していたオーストリア軍との戦いの末に、ナポレオンはウィーンへの進軍を始めた。オーストリアはフランスとの講和を求めるようになった。その条件として、ネーデルラントの南部をフランスに割譲した。
カンポフォルミオ条約によって、イタリアでの5年間の戦争は終結した。このとき、ナポレオンの人気はいよいよ高まった。
エジプト遠征:発掘ブームへ
1798年、ナポレオンはイギリスとの戦いを考えた。だが、イギリスへの上陸作戦はハードルが高かった。
そこで、まず、イギリスとそのインド植民地の通行を妨害する作戦を選んだ。そのために、エジプトに遠征した。アレクサンドリアの占領に成功した。

ナポレオンはカイロでエジプト研究所を設け、エジプトの研究を学者たちに開始させた。その後、イギリスの海将ネルソンと戦い、敗北した。ナポレオン自身はエジプトから本国に戻り、エジプト遠征を部下に任せた。結局、イギリスに敗北した。
なお、このエジプト遠征により、ヨーロッパのエジプト研究が本格化していく。イギリスとフランスを中心とした発掘ブームなどが起こることになる。
ブリュメール18日のクーデター:フランスの執政へ
フランス国内は依然として混乱していた。『第三身分とはなにか』で革命を訴えていたシェイエスは、ナポレオンとともにクーデターを試みた。1799年、二人はブリュメール18日のクーデターを成功させ、執政政府を樹立した。
同時代のフランス人は、右翼も左翼もこれに反対しようとした。右派の人々はこのクーデターをそれまでの革命の急進化と解釈した。対照的に、左派の人々はこのクーデターを革命からの完全な断絶と見なした。
体制の安定化
この時期には、フランスは内部対立が長らく続いていた。王党派と革命派の対立だけでなく、革命派もまた内部で対立していた。この分裂状態を改善すべきだと考えられてきたが、なかなかうまくいかなかった。
ナポレオンはクーデター後、自身がこの分裂を癒やしフランスに安定をもたらす「救世主」としてふるまった。ナポレオンだけが、様々な派閥間の闘争と対立に終止符を打つことができる。そのような者として自己をアピールした。
実際に、有能で忠実な者なら、どのようなイデオロギーや派閥の者であっても、登用し始めた。
各方面の支持者をえることで、ナポレオンの新体制は安定していった。同時に、アメとムチの政策をとった。国家と市民への暴力をもたらす者には、公開処刑などで厳しく対処した。
ナポレオンは軍事委員会を設置し、盗賊や反抗的な農民、敵対者などを処罰した。1801年から1804年にかけて、特に厳しい弾圧を行った。 この間、軍事法廷は毎年800人以上に死刑を宣告し、さらに3,000人に重労働を課した。
ナポレオンは新聞などの報道を弾圧した。だが、市民はあまり反発しなかった。新聞などの報道の自由が派閥の分裂や対立を助長したと考えていたためだった。ナポレオンは情報統制と同時に、国民の和解を目的に、新聞への弾圧を加えた。
国内制度の整備
ナポレオンの軍事独裁が始まった。彼は財政や司法、警察などの様々な改革を進めた。フランス学士院やリセ(高校)の創設、大学の仕組みの整備などによって、教育や研究の制度を整えていった。
優れた人材を育てるために、レジオン・ドヌール勲章を創設した。ほかにも、フランスの諸制度を近代化していった。
1802年、ナポレオンを終身の執政にするかどうかの国民投票が行われた。これは不正に操作されたものではあったが、圧倒的多数が賛成だった。だが、ナポレオンへの暗殺計画が露見するなど、不安定でもあった。
ローマ教皇との政教協約
1801年、ナポレオンはローマ教皇ピウス7世と政教協約を結んだ。これはフランスの教会をめぐって、ナポレオンとローマ教皇の関係を規定するものである。
中世以来、教皇はフランスの教会の人事権などをもつと主張し、フランス王と対立や交渉を繰り返してきた。ナポレオンの政教協約はその一環である。

政教協約はナポレオンの成果の一つとして認知されている。そこでは、教会所有地の国有化を合法化した。さらに、国家は宗教問題においては中立を保つとして、宗教的寛容の原則を明確に確立した。
そのようにして、フランス革命の成果を維持した。さらに、ナポレオンは教会を国家が支配すべきと考えていたので、教会への統制を強めようとした。
ナポレオンはこの政教協約の成果を公表するタイミングで、特別な条項を追加して公表した。これは教皇の同意を得ていないので、政教協約の一部とは言い難い。だが、その一部であるかのように公表した。
そこでは、 教皇がフランス教会の多くの分野に介入する権利を持たないとされた。革命中の教会財産の喪失を正式に確定した。教皇とフランス聖職者とのすべての連絡をフランス政府の厳格な管理下に置くことになった。
1804年、ナポレオンはフランスを帝国であると宣言し、自ら初代皇帝についた。
なぜ帝政だったのか。フランスは革命開始後、立憲王政への移行を模索した。だが、王のヴァレンヌ逃亡事件などをきっかけに、共和主義者が実権を握った。
王のルイ16世を処刑するとともに、フランスを共和制に移行させた。だが、フランスは内戦に至るほどの分裂状態を経験し、苦しんでいた。政治的エリートの中には、立憲君主制に戻りたいという者も少なくなかった。
帝政の選択は、急進的な共和制と君主政の間の第三の道を意味した。ナポレオン自身は君主制を志向した。共和制は国際的にも評判が悪く、フランスはそれが一因で国際舞台でなかなか受け入れられなかったためだ。
とはいえ、ナポレオンは立憲君主制には戻るつもりはなかった。「人民主権」という革命的原則に当初は基づいたかたちで、革命開始後の様々な失敗の過去とは離れるべく、帝政という新しい形を選んだのだった。
ただし、ナポレオンが皇帝として定着するにつれて、次第に共和主義の人民主権的な要素は弱まっていく。
フランス革命が求めた「国民」は旧来の臣民になった。ナポレオンがフランス人の父としてふるまうようになる。このように、ナポレオンの帝政はアンシャン・レジームのフランス王制に近づいていく。
ナポレオンの戴冠式
1804年、ナポレオンは教皇から戴冠されるよう手配した。皇帝が教皇から戴冠を受ける儀式は、800年の神聖ローマ皇帝のカール1世の時代に始まる由緒ある儀式だった。ナポレオンは威厳を高めるために、この戴冠式を利用することにした。
教皇ピウス7世はパリのノートルダム大聖堂に到来し、戴冠式を行った。ナポレオンはこの様子を画家ダヴィドに描かせ、絵画を自身の権威のために利用した。
ただし、実際には、教皇自身が冠をナポレオンの頭の上に載せたわけではなく、ナポレオンが冠を自分の手で自分の頭に載せたといわれている。
しかし、これでは画題にはふさわしくないので、ダヴィドの絵画はそのように描かれていない。すなわち、事実を正確に描いたものではない。

ナポレオン法典
ナポレオンの国内政策の成果として、ナポレオン法典の編纂があげられる。このような国内の統一的な法体系を整備するという構想は1789年の革命の初期段階から存在していた。
1791年には、新しい法典の制定が着手された。 1793年から1796年まで、3度にわたって法典が議会に提出されたが、採決されなかった。
ナポレオンは政権をえると、法典編纂のために、4人の委員を任命し、作業を始めさせた。ナポレオン自身はこの法典を社会的結束の道具とみなしていた。
1801年に原案が完成し、審議と修正のために国務院に渡された。ナポレオンは3年間にわたり、法典審議の会議の半分以上に参加した。
ナポレオンは委員会のメンバーの意見に耳を傾け、しばしば質問をした。ナポレオンが法典の中身にどれだけ影響を与えたかについては歴史家の議論が割れている。
ナポレオン法典の意義は、フランス近代国家の基礎となったことである。ナポレオン自身が没した後でも、この法典はフランスの法的基礎として残り続ける。そこでは、法の下の平等の原則、封建制の廃止、社会の基盤としての家族などの特徴がみられた。
ただし、女性と子どもの権利にかんしては、ナポレオン法典は革命の原則に反し、アンシャン・レジームに近づいた。この法典は父権主義的である。
1792年の法律で、女性は家庭内での平等の地位を認められるようになった。だが、ナポレオン法典により、たとえば、結婚や財産に関する女性の権利は制限された。あるいは、父親は、理由を示すことなく、最長6ヶ月間、子供を堕胎させることができるようになった。
対外政策:拡張政策
対外的には、ナポレオンはドイツやオーストリアでの戦争で戦果をあげた。その後、1802年にはすべての国との戦争を終わらせた。その後、対外拡張を再開した。カリブ諸島では、トゥサンがハイチ革命を始めたサン・ドマングを取り戻した。
イタリアやオランダで実権を握ろうとし、スイスで勢力を拡大した。1803年、イギリスはナポレオンの動きを容認できず、フランスとの戦争を開始した。イギリスはフランス国内の旧・王党派への支援を再開した。ナポレオンへの暗殺計画が露見した。
トラファルガーの戦い:イギリスとの一大決戦
ナポレオンはイタリア王国を樹立し、その国王となった。さらに、最大のライバルのイギリスとの決戦を準備した。いよいよイギリス本島への攻撃を仕掛けるのである。この決戦が、1805年の有名なトラファルガーの戦いである。
ナポレオンはスペインを味方につけて戦いに挑んだ。だが、イギリスの英雄ネルソン提督に敗北した。イギリスを征服することはできなかった。ただし、ネルソンはここで戦死した。

神聖ローマ帝国を滅ぼす
それでも、ナポレオンはオーストリアやロシアなどとの戦争で勝利を重ねた。オーストリアはイタリアから追い出されることになった。ロシア皇帝とは一時、和解した。
1806年、神聖ローマ皇帝軍を打ち破り、皇帝を廃位した。かくして、神聖ローマ帝国は滅び、その長い歴史の幕を閉じた。
その他の進撃
イタリアでは、ナポレオンは教皇領を占領した。1808年、スペインの征服を試みたが、成功しなかった。
ナポレオンはこのように同盟国だったスペインを攻撃した。そのため、どの国もナポレオンを信用できないと感じた。ナポレオンの対外拡張は様々な方面に及んでいたので、各国はナポレオンに危機感を抱いていた。
ナポレオンはポルトガルを征服した。ポルトガル王室はブラジルに逃げ延びた。1810年、ナポレオンのフランス帝国は広大な領土を誇った。ナポレオンの人気は極まった。
敗北と島流し
しかし、1812年、ナポレオンは劣勢に追い込まれることになる。ロシア遠征で、ロシアの強烈な「冬将軍」を前に、敗北を喫した。
これを機に、ナポレオンへの反乱が諸国で活発化した。翌年には、ナポレオンの敗北は濃厚となった。敵対国の連合軍はパリにも迫った。1814年、ナポレオンは皇帝の退位を余儀なくされ、エルバ島に流された。
百日天下と完全な失墜:ワーテルローの戦い
だが、ナポレオンはエルバ島からの脱出に成功した。1815年にはパリに戻ってきた。彼は再び実権を握ることに成功し、いわゆる彼の「百日天下」が始まった。対外戦争を再度試みた。
しかし、ナポレオンはベルギーでのワーテルローの戦いに破れた。ここで、ナポレオンの命運は尽きた。再び皇帝の退位を余儀なくされた。

セントヘレナ島でイギリス軍に捕まり、そこが終の棲家になった。1821年、同地で没した。死後、ナポレオンはフランス革命の擁護者として称えられた。
ナポレオンの評価
ナポレオンはフランス革命の敵か味方か
ナポレオンはフランス革命の敵だったのか、あるいは味方だったのか。このような評価が長らくなされてきた。
革命の敵だと評される場合、その根拠は次の通りである。報道への検閲、選挙と代議制が実質的に欠如していたこと、新たな貴族を創設したこと、対外的な拡張主義政策である。
これにたいし、革命の味方だったとされる場合、根拠は次の通りである。封建制度とそれに伴う貴族の特権の廃止、国家への宗教の従属(教会所有地の国有化など)、今日まで続く教育制度と国家機関の設立、統一通貨制度の導入などである。
ナポレオンは独裁者か否か
ナポレオンは皇帝として権力を安定させるにつれ、独裁的になっていった。1807年が特にその転機として指摘されてきた。では、ナポレオンは独裁政治に至ったのか。この点については、歴史家の意見は割れている。
ナポレオンを独裁的と評価する声は多い。たとえば、ナポレオンはルイ14世の絶対王制以上の絶対主義であった。古代ローマのユリウス・カエサルと同等である。あるいは、啓蒙専制君主の一人である。
他方で、ナポレオンの別の側面を指摘する声もある。ナポレオンは民主国家のルイ14世である。民主化された絶対主義者である。あるいは、ナポレオンの帝国は権威主義的警察国家であるとか、自由主義的権威主義である、と。
ただ、少なくとも、ナポレオンを単に専制主義と呼ぶのは不正確である。 政治的な罪で投獄されたのはせいぜい数百人である。これは恐怖政治の時期に比べればかなり少ない。政治的な理由で恣意的に処刑された者はわずかだった。
さらに、ナポレオンの政権は、国民投票や限定的な選挙手続を利用した。この点では、当時のヨーロッパ大陸のどの政権よりもはるかに民主的であったと評されている。
ナポレオン1世と日本
日本人がナポレオン1世を最初に知ったのはおそらく1812年のことである。当時、日本はヨーロッパ諸国の中ではオランダのみと公式の交流を行っていた。
だが、ロシアはエカチェリーナ2世の頃から積極的に南下政策を開始し、1792年にはラクスマンらを日本へ派遣して日本との通商を実現しようとしていた。
他方で、1808年にはヨーロッパ最大の海洋帝国だったイギリスもまた日本に到来し、フェートン号事件を長崎で起こしていた。林子平が『海国兵談』を著すなど、日本でのこれらの国への危機意識が表面化していった。
このような状況下、1812年、いわゆるゴロウニン事件で日本に到来したロシア人を通して、幕府はナポレオン1世を知ることになった。
その後も、幕府はオランダ人からナポレオン1世について聴取した。19世紀初頭の日本はイギリスやロシアを外的脅威とみなしたため、ナポレオン1世は日本自身の関心を惹起した。
長崎の天文方がナポレオン情報の収集を行い、1820年代にはナポレオンの伝記を公刊した。その後も、天文方ではナポレオンの情報収集が続いた。このような動きが他の藩にも見られるようになる。
また、伝記を読んで感銘を受ける者も出てきた。佐久間象山や吉田松陰、頼山陽らはナポレオンの漢詩を制作した。
ナポレオンは次第に、内憂外患の日本の危機を乗り越え、イギリスとロシアの外敵から日本を解放する救世主のような人物とみなされるようになった。原因は当時のフランスと日本の状況の類似性や、ナポレオンの生い立ちと大躍進にあった。
上述のように、ナポレオンは弁護士の家庭のうまれだった。両親は貴族の末裔だったが、小貴族だった。当時のフランスは1789年のフランス革命とその後の干渉戦争によって、内憂外患だった。だが、ナポレオンの軍事的活躍のおかげで、フランスは周辺国の攻撃を押し返した。
さらに、周辺国への進出を開始し、ドイツやオーストリア、ポルトガルなどを制圧していった。ナポレオンはついには皇帝に成り上がり、トラファルガーの戦いではイギリス本島にも攻撃を仕掛けた。さらに、ロシアとも戦争を開始した。
このように、イギリスなどにたいする目覚ましい軍事的活躍でフランスを内憂外患の危機から救い出し、その功績により、皇帝への即位というフランスの伝統的な身分秩序のもとでは不可能なほどの出世をした。
幕末の日本で活動した大半の志士たちもまた、江戸時代の身分秩序ではたいした出世の見込めない低い地位の出身者だった。フランス革命でのフランスと同様に、幕末の日本もまた内憂外患だった。
国内では薩長同盟と幕府の戦いにまで至る一方で、ロシアやイギリスなどの外敵脅威に脅かされていた。このような状況で、自身の軍事的活躍によって日本を内憂外患の危機から救い出し、その功績によって低い身分から一気に出世できたなら・・・。
たとえば、佐久間象山は「題那波利翁像詩」という漢詩でこう述べている。ナポレオンはもともと身分の低い者であった。だが苦学して身を立て、頭角を著した。旧弊をあらため、民に幸福をもたらした。
さらに周辺国を征服しては、フランスの威信をヨーロッパ全体に示した。最後はロシア遠征で敗れた。だが、もしこのような英雄が今日に日本にいたならば、全世界の五大陸を天皇のもとに帰属せしめることができるだろう、と。
ナポレオンは幕末日本において、このような救世主のモデルとして受け入れられた。
ナポレオン1世の肖像画占領に成功した。
ナポレオン1世と縁のある人物
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
ナポレオン1世の肖像画
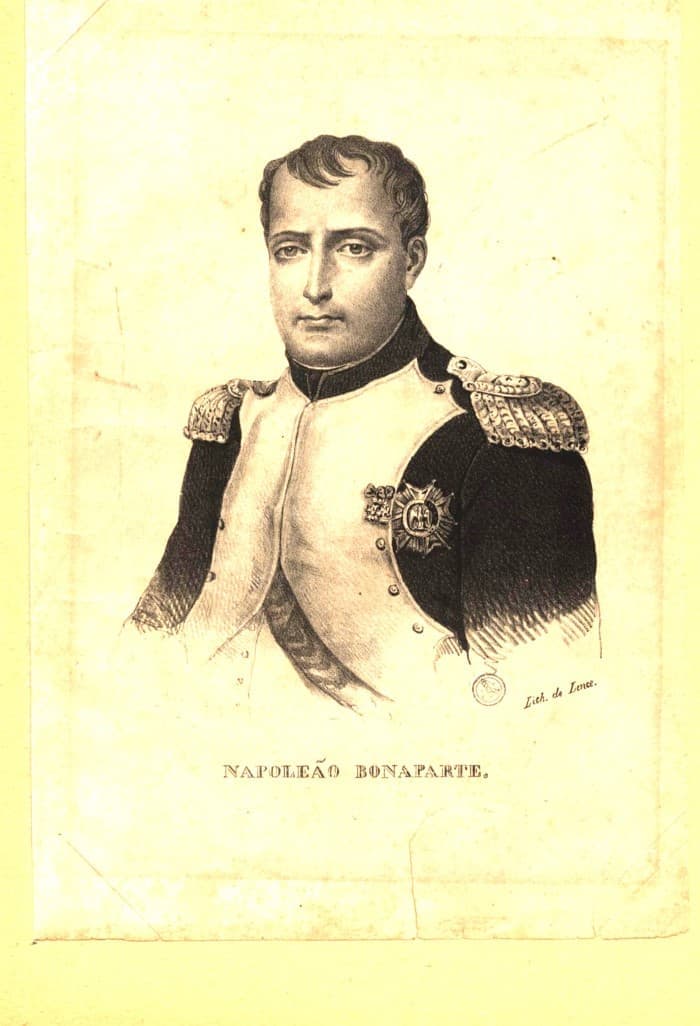
おすすめ参考文献
杉本淑彦『ナポレオン : 最後の専制君主、最初の近代政治家』岩波書店, 2018
上垣豊『ナポレオン : 英雄か独裁者か』山川出版社, 2013
岩下哲典『江戸のナポレオン伝説』中央公論新社, 1999
Lynn Hunt and Jack Censer, The French Revolution and Napoleon : crucible of the modern world, Bloomsbury Academic, 2022
François Lachaud(ed.), D‘un empire, l’autre : premières rencontres entre la France et le Japon au XIXe siècle, École française d’Extrême-Orient, 2021
David Andress(ed.) (2019) The Oxford handbook of the French Revolution, Oxford University Press




